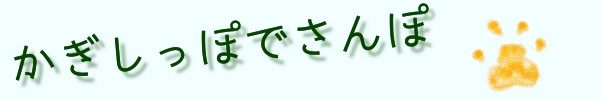2019年大晦日、住まいの地域は実に良い夜空が広がっていた。家から外に出ると、除夜の鐘が冷えた空気を渡り聞こえて来た。
夜の宝石が瞬く中、近所の熊野神社へと足を運ぶ。全国に3000社あるうちの一つ。
道路に車も少なく、いつにも増してしんと静まり返った町は、冬の張りつめた緊張感とともに神聖な雰囲気も漂っていた。
2020年は神社に行く最中に迎えた。
さぁ初詣だと言わんばかりにいそいそと神社へと向かう人もいれば、すでに終えてそこから帰っていく人とすれ違いながら、神社に到着。老若男女問わず参拝者が列を成していた。
例年、その列ができる脇で温かい飲み物が振舞われる。順番を待っている間、一緒に初詣に来た人と何か飲み物を貰おうか、何にしようかという会話をするのも毎年恒例の流れだ。
待っている間に飲み物を貰うか、お参りしてから貰うかは人それぞれ。
待ち時間の途中に気が付いたが、参道の脇にモニターが設置され、映像が流れていた。中継とかではなく、熊野神社での七五三の動画が流れている。幼子が横に座る神主をちらちらみながら、見よう見真似で同じ動きをしている様子が何とも愛らしかった。
去年まではモニターは無かったが、突如現れた利器は些か目立つ。けれど、初詣というイベントに浮かれているばかりではなく、お参りに来ているという認識を改めてする厳格さは醸し出されていた。
手水舎で清め、参拝してから飲み物を戴く。
チョコの誘惑的な香りを放つホットココアに、これも温かい紅茶類が用意されている中、堂々とした大鍋を神社の法被を着たおじさんがかき混ぜている。それは甘酒だ。
甘酒はこれまで何度か飲んでいるが、ちょっと好まない味だと思っていた。
なんというか、酒の匂いのするとろとろのお粥を飲んでる、といった感覚で快か不快かでいえば後者だった。飲めばあのとろとろが、そのまま胸と胃に沁みついたように気持ち悪くなる感覚。
ところが何ということだ。美味しいではないか、甘酒というやつは。
前までは感じられなかった、優しい甘みが突如として感じられるようになった。
これなら毎日でもいけるぞ!
大人たちはこの甘さを噛みしめていたのだな…(?)。
しかし、一口に肉じゃがと言っても家によって味の濃さや具材が違ったりするように、ここで振舞われる甘酒が特別に美味しいのでは…?
ともかく甘酒は美味しい。これが新年始めに衝撃を受けたことだった。
掲示板はいつもあまり気に留めず、他の人も素通りする。ふとそこに目を留めた。掲示板の内側にあるライトに煌々と照らされた用紙には、このようにあった。(一部抜粋での記載だった)
初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やわら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かをら)す。
萬葉集にある和歌で、元号「令和」の由来となっている。
書き手は不明だが、山上憶良(やまのうえのおくら)作ではないかと言われているらしい。山上憶良は歴史の授業で習った記憶がある。いや、国語か古典の授業だったか?「憶良」という漢字の並びが、とても好きだったのを覚えている。もちろん今もそう思う。
和歌についての詳細はこちら:万葉集入門
日本という国は歴史がとても長く、国民でさえ自分の国のことをよく知らない。しかし、昔のその時を生きた人々の言葉を現代に再び咲かせることで、先人たちが積み上げた歴史を感じ取ることができる。
西暦2020年、和暦では令和二年。もう二年になるのかと平成生まれは驚きを隠せない。
元号が新しくなるという経験はそうそうないことで、昨年五月一日に元年となったばかりだと思っていたら、もう数字が増えている。例えるなら、夏休みが終わったらすぐに冬休みになるというような早さ。
筆者が掲示板を眺めていると、後ろで人が立ち止まったのが足音で分かり、すぐに立ち退いた。
後でそっと振り返ると、紙コップ片手に掲示板を見ている少年が掲示板のライトの明かりで浮かび上がっていた。和歌の他にも貼り紙があったから、何を見ているのかは分からなかったが、萬葉集の方を見てくれているなら少しばかり嬉しい。
なんかよく分からん事書いてる、とスルーするのは悲しい。途方もない時を越えても和歌が生き残っていることや、元号に関係しているのだから。
きっと時事問題として、社会科の先生が期末考査とかに出題することだろう。
というより、何故彼は立ち止まったのだろう。人が見ているものが気になったとか?
冬の大三角を眺めながら、熊野神社から家へと帰った。